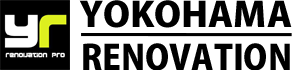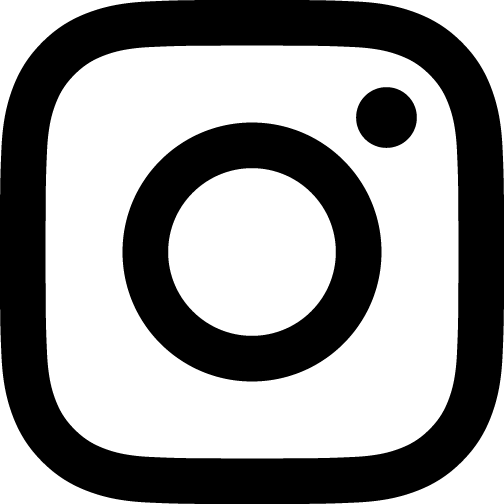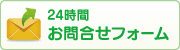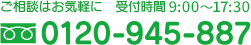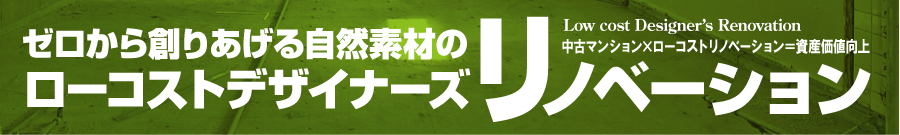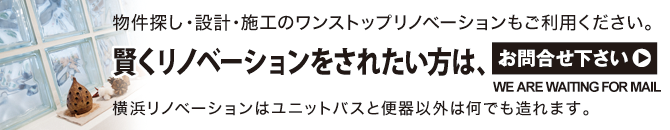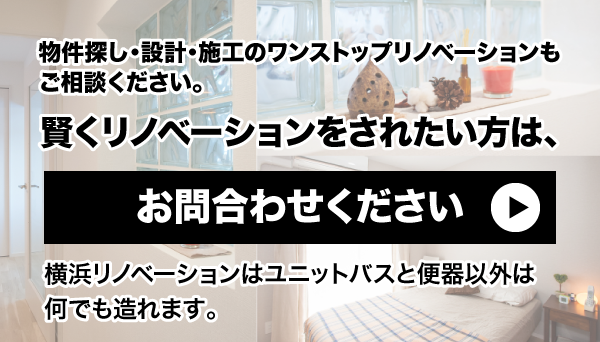家の中で、床は触れる時間がもっとも長い場所です。
だからこそ、せっかくリノベーションするなら、肌ざわりがよく身体にもやさしい『無垢フローリング』を取り入れたいですよね。しかし、無垢材はすべての人に向いているわけではありません。特性を知らないまま採用すると、「こんなはずじゃなかった」と、後悔することも。メリットやデメリット、注意点を知ったうえで取り入れる必要があります。そこで今回のコラムでは、無垢フローリングの基本と失敗しないためのポイントを説明します。ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも『無垢材フローリング』とは?
まずは無垢フローリングとは何か、基本部分を説明します。
無垢フローリングとは?人気な樹種

無垢フローリングは、天然木をそのまま切り出してつくった床材のこと。
1枚板でできているため、木の質感や温もりをしっかりと感じられるのが特徴です。
そしてひとくちに「無垢材」といっても、広葉樹か針葉樹かで、次のように特徴が異なります。
- 広葉樹:強度があり、耐久性に優れている。針葉樹よりも費用が高くなりやすい。
- 針葉樹:やわらかく、肌ざわりが心地よい。傷つきやすい。
また、無垢フローリングで人気なのは、次のような樹種です。
- 広葉樹:オーク(ナラ)、クリ(チェスナット)
- 針葉樹:スギ、ヒノキ、マツ(パイン)
樹種だけでもさまざまな種類がありますが、そこから節の出方や色味、グレードなども決めていくため、選択肢は多岐にわたります。
複合フローリングとの違い
複合フローリングは、合板の上に薄くスライスした天然木や、化粧シートを貼り付けてつくられた新建材です。建売住宅やマンションで多く採用されています。
メリットは、反りや割れのリスクが少なく、初期費用を抑えられることです。表面が天然木になっている『突板フローリング』や『挽き板フローリング』を選べば、無垢材に近い質感を愉しむこともできます。
ただし、耐用年数は10~15年ほどと無垢フローリングよりも短く、物を落としたときに傷が深ければ、基盤が見えてしまうことも。修復の難しさがデメリットです。
【関連記事】リノベーションするなら知っておきたい、無垢床と複合フローリングの違い
リノベーションで無垢フローリングを選ぶメリット

リノベーションで多くの方が無垢フローリングを選ぶのは、次のようなメリットがあるからです。
自然素材ならではの温もりと質感を愉しめる
天然木を切り出してつくられた無垢フローリングは、木ならではの質感やぬくもりを感じられます。木目や節の様子など、まったく同じものがないのも魅力のひとつです。
冷暖房などに頼りすぎない暮らしができる
無垢材は表面に小さな穴がたくさん空いており、そこから湿気を吸収したり、放出したりします。さらに穴が空気層になって熱を伝えにくくするため、断熱性に優れているのも特徴。冬に冷っとした寒さを感じにくく、夏時期でもさらっと心地よいのは、この性質によるものです。
また、蓄熱効果もあるため、暖房を消したあともほんのりと暖かさが続きます。
経年変化・美化を感じられる
無垢フローリングは、経年とともに色味が変わっていきます。黄色味が増したり飴色に変わったり、こげ茶色に変わるものも。こうした変化を愉しめるのも、無垢材を選ぶメリットです。
「色が変わるのは嫌だ」という方は、仕上げにオイルを塗れば色変わりを防げます。
メンテナンスコストが低い
複合フローリングの耐用年数が10~15年なのに対して、無垢フローリングは正しい施工と適切な手入れを行えば、耐用年数は50年以上。長期間にわたって張り替えは不要です。
また、小さな傷や凹みならサンドペーパーで削るか、スチームアイロンを当てるだけで補修できるので、自分でメンテナンスできます。
初期費用は高くなるものの、長い目で見ればコストパフォーマンスのよい素材と言えます。
住まいの資産価値が向上する
ここまで説明したように、無垢フローリングには性能面にさまざまなメリットがあるため、採用すれば住まいの資産価値が高まります。
とくに複合フローリングが使われることが多いマンションにおいては、無垢フローリングを使った部屋は他の部屋にはない付加価値があります。
万が一売ることになった際にも、リノベーションしていない部屋よりも高値で売却できるでしょう。
【関連記事】マンションリノベーションで楽しむ、無垢フローリングの魅力
【関連記事】資産価値を高めるマンション・戸建てリノベーションを成功させる4つのポイント
リノベーションで無垢フローリングを選ぶデメリットと注意点

無垢フローリングに決定的なデメリットはありませんが、木の特性を知らずに選ぶと「想像と違う」と、感じるかもしれません。ここで注意点を知り、無垢材が自分たちの価値観に合うのかを考えてみてください。
反りや変形のリスクがある
無垢材は調湿性がある一方で、湿度や気温の変化による影響を受けやすい素材です。
湿度が高いときには膨んで、逆に乾燥しているときには縮み、湿度の変化に応じて膨張と収縮を繰り返すため、その際に反りや変形が起こってしまうことも。
軽度の反りならアイロンや濡れふきんを使って自分で補修できますが、大きな反りや割れが起こると、業者への依頼が必要です。
場合によっては張り替えが必要になるケースもあるため、症状が軽度なうちに対処しなくてはなりません。
傷や凹み、シミなどができやすい
無垢フローリングは、傷や凹み、シミなどができやすいのがデメリットです。
とくにスギやヒノキ、パインのような針葉樹はやわらかいので、物を落としただけで傷や凹みができてしまいます。そのため「引き渡しから1年足らずで傷だらけ」といったケースも少なくありません。
また、水や油が染み込みやすいのも難点です。すぐに拭き取って乾燥させなければ、あっという間にシミができてしまいます。遠目で見れば目立ちませんが、気になる方はウレタン塗装の検討を。
「どうしても汚したくない」という方は、キッチンや洗面などの水まわりだけは違う素材にするか、マットを敷くのも一案です。
しかし、こうした変化も無垢材の醍醐味のひとつ。
床にできた傷や凹み、シミを“味”ととらえるか、“劣化”と感じるかの価値観の違いが、無垢フローリングが合うかの分かれ道になります。
初期費用が高くなりやすい
無垢フローリングは複合フローリングよりも材料費や施工費が高くなるため、どうしても初期費用も高くなります。メンテナンスコストやコストパフォーマンスには優れているものの、「初期費用を抑えたい」と考える方にとっては、デメリットに感じるかもしれません。
無垢フローリングを取り入れつつも費用を抑えるためには、次のような方法があります。
- 比較的安価なアカシアを選ぶ
- 節が多いものや色むらのあるも商品(ミドル・低グレード)を選ぶ
また、過ごす時間が長いリビングや寝室などだけに無垢フローリングを使い、他は複合フローリングにすれば、費用を抑えられます。
【関連記事】無謀な予算決めはNG!その予算で何ができるか考えてみよう
マンションでは防音性の規約がある
マンションにはさまざまな管理規約があり、床材にも遮音等級の制限がある場合がほとんどです。複合フローリングは遮音性能が高い商品も多いですが、無垢材は遮音性が高くありません。管理規約を満たすためには、床全体を上げてコンクリートスラブとの間に空間をつくる『置き床工法』にするか、床下にクッション材を敷くなどの遮音対策が必要です。
どの方法が適しているのかは物件や予算によっても変わってくるので、リノベーション会社と相談しながら検討しましょう。【関連記事】マンションリノベーションでは後悔も多い…失敗しないためのポイントは?
リノベーションで無垢フローリングを選ぶときのポイント
最後に、リノベーションで無垢フローリングを選ぶときに失敗を防ぐポイントを説明します。
無垢フローリングの知識と施工技術が高い会社に相談する
デメリットの章で説明した反りや変形は、湿度や気温の影響が大きいですが、施工状態によって起こることも。たとえば、床材を隙間なく敷き詰めてしまうと、膨張時に反りやすくなり、乾燥が不十分な無垢材を使うと、変形のリスクが高まります。こうしたトラブルを防ぐためには、無垢材の特性を熟知し、扱いになれているリノベーション会社に相談するのが重要です。
全面同じ樹種にする、施工場所や予算によって床材を変える
無垢フローリングは樹種によって木目や色味、硬さなどが異なるため、「部屋ごとに分けたい」という方も多くいます。しかし、樹種を変えると発注の関係で、費用がかさんでしまうことも。費用を抑えつつ無垢フローリングを選びたいなら、全面同じ樹種にするのがおすすめです。
それでも予算が難しいときには、部分的に取り入れる方法もあります。
たとえば、過ごす時間が長いリビングに取り入れ、他の部分は複合フローリングにするなど、施工場所によって床材を変えれば費用を抑えられます。
【関連記事】リノベーションで無垢材をポイントに入れるとおしゃれ!
リノベーションで無垢フローリングを選びたい方は、横浜リノベーションにご相談ください
住まいに無垢フローリングを取り入れれば、自然素材ならではの心地よさや温もりを感じられます。暮らしの快適性が増すのはもちろん、資産価値の向上につながる点もメリットです。長い目でみれば、コストパフォーマンスにも優れています。
性能面に優れている分、どうしても初期費用は高くなってしまいますが、比較的安価な樹種を選んだり、使う場所を限定したりすれば費用を抑えることも可能です。
その点も含めて、無垢材の特性を熟知し、扱いに慣れている横浜リノベーションにご相談ください。
ただいま25組限定でモニター募集中です!特別価格にてリノベーションするチャンスなので、お気軽にご相談ください!
▶モニタープロジェクトの詳細はこちらから
Instagramも運営しておりますので、こちら↓をクリックして「フォロー&いいね」をよろしくお願いいたします!